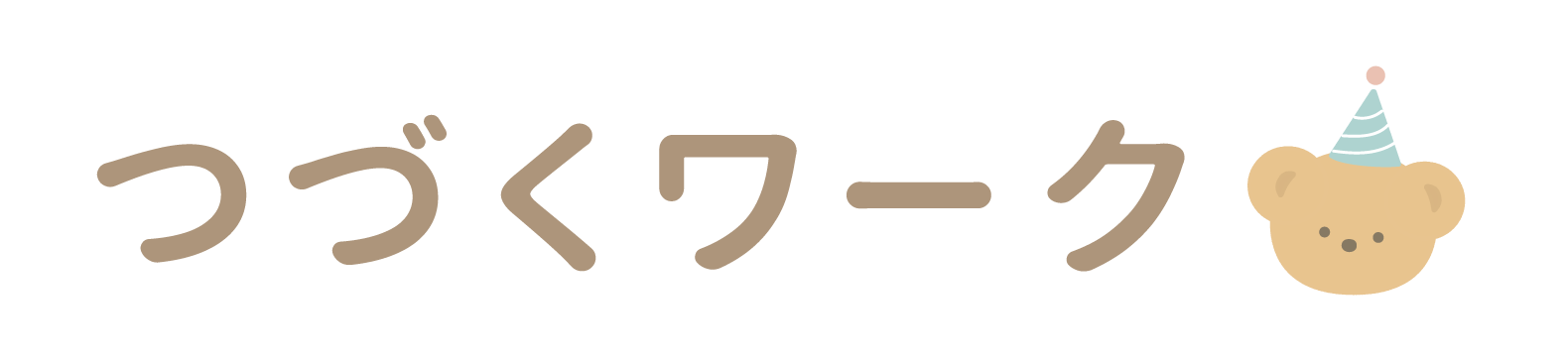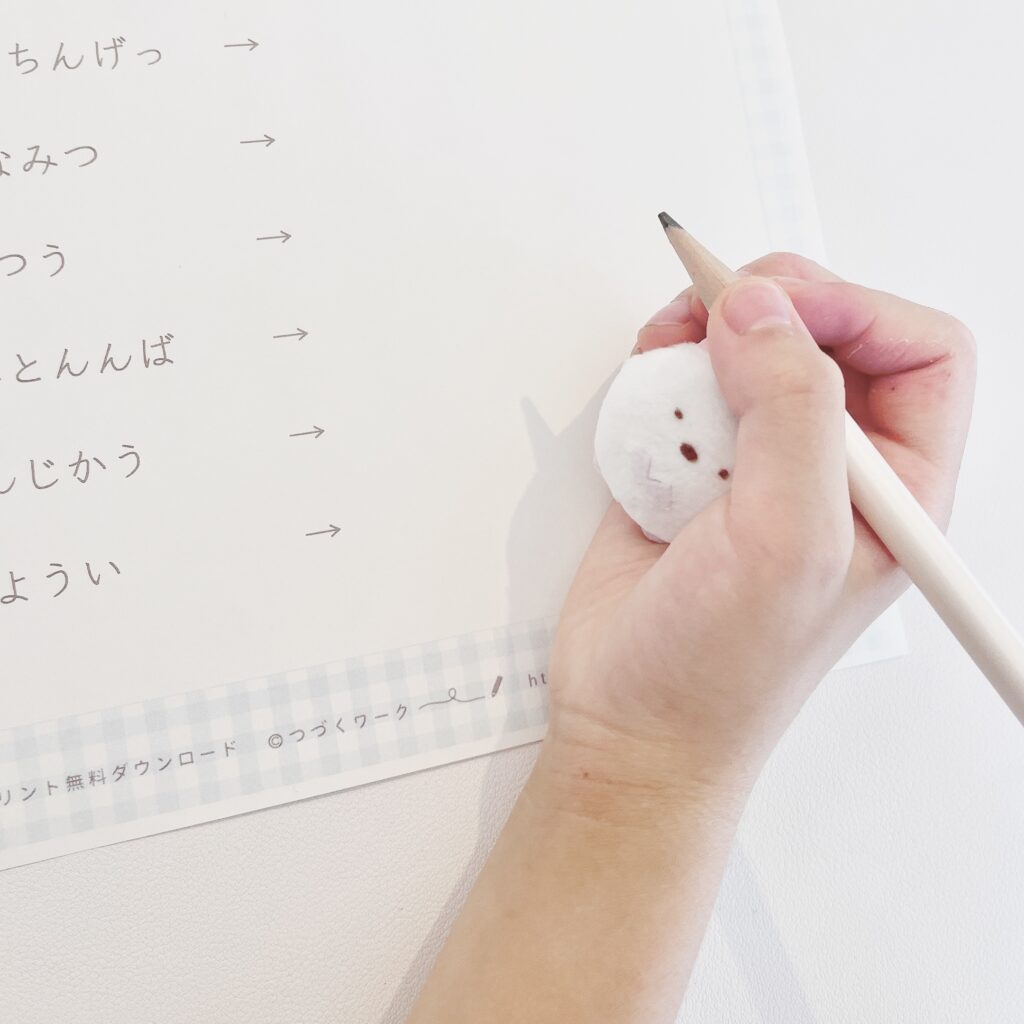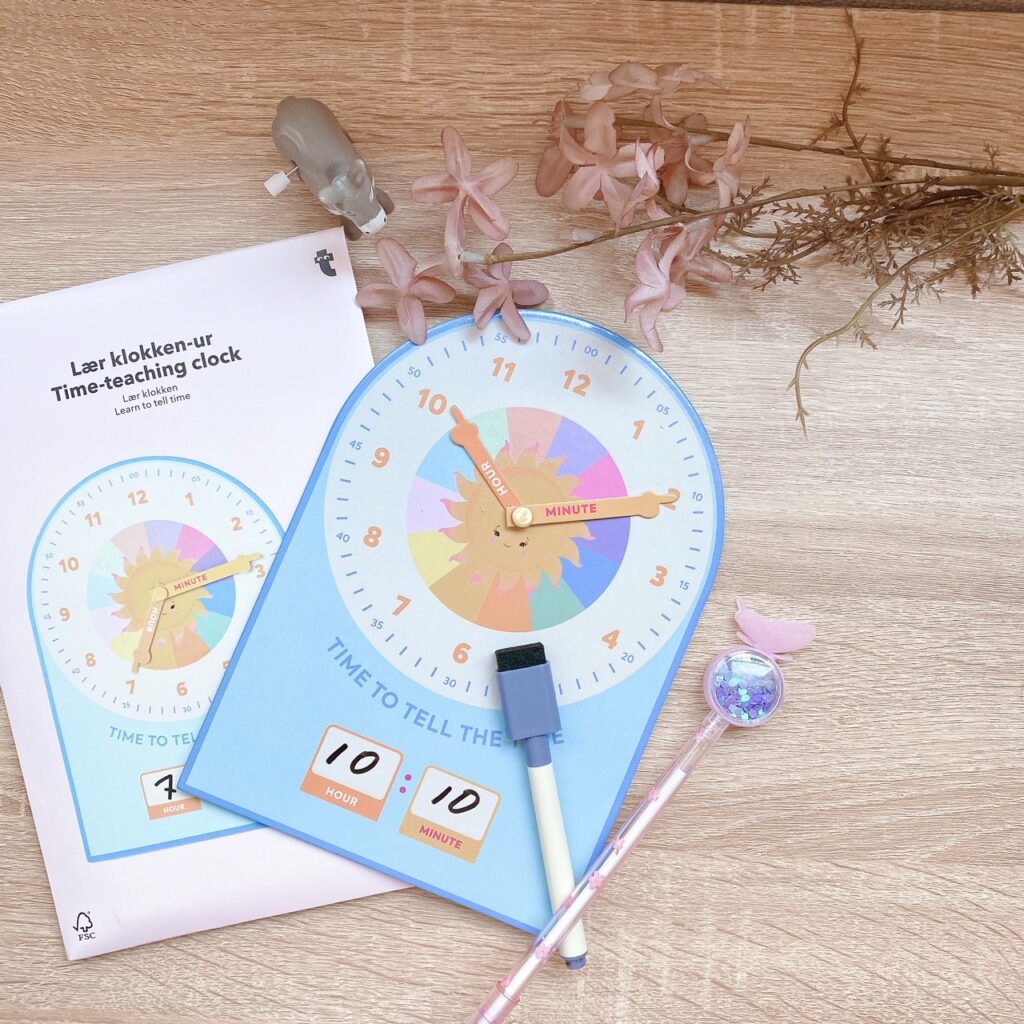こんにちは!つづくワークです。
子どもと本のある時間は、特別なものだと思います。
読み聞かせをしながら、声に出してセリフを読んだり、イラストを見て一緒に笑ったり。それは、小さな子どもが言葉やものに興味を持つ、大切な入口なのかもしれません。
かく言う我が家も、1歳半から通っていた『babyくもん』で先生に『絵本の読み聞かせは絶対!読めるだけ読みなさい』と言われていたので、幼児期から沢山の絵本や図鑑を一緒に読んできました。
(babyくもんでは、毎月『くろくまくん』の絵本と、ワークブックをいただき、おうち時間に活用します。)
幼児期の読書は、「読み書きの準備」や「語彙の習得」といった知育的な側面が注目されがちですが、実際に日々絵本を読みながら感じたのは、子どもの思考や感情が、ゆっくり立ち上がっていく過程を見ているような感覚でした。
今回は、幼児期の各段階で、読書が幼児期の知的な発達にどう作用していたか、読んでよかった絵本を、ひとつの記録としてまとめてみたいと思います。
絵本の好みや食いつきは、お子様によって違うと思うので、ひとつの参考として見て頂ければ幸いです✨
1. ことばの土台が育つ、最初の本(0〜2歳)
発語できるようになる2歳までは、音やリズムを楽しむ絵本を中心に読み聞かせしました。
選ぶポイントとしては、【繰り返しが心地よく、記憶に残る本】でしょうか。
生後0〜1歳ごろ(ことば以前の感覚を育てる時期)
| タイトル | 特徴 | 知育ポイント |
|---|---|---|
| 『じゃあじゃあびりびり』 まついのりこ(偕成社) | 身近な音がいっぱい | 音と意味の関連づけの第一歩。聴覚と視覚の刺激に。 |
| 『いないいないばあ』 松谷みよ子(童心社) | 繰り返しの安心感 | 対人関係の基本となる「やりとり」の感覚が育つ。 |
| 『もいもい』 市原淳(こぐま社) | 赤ちゃんに魅力的な色と動きが沢山 | 視線を誘導する形・色・配置が工夫されており、視覚的認知の力を育てる。 |
| 『しましまぐるぐる』 かしわらあきお(学研プラス) | コントラストがはっきりした色と、擬音 | 擬音や繰り返しのことばが多く、言語理解の土台をつくる。 |
どれも名作絵本ですが、この中で一番のおすすめ絵本は『もいもい』です!
この本では、出てくる言葉は『もいもい』だけなのですが、刺激的なイラストに合わせた色々なシチュエーションで『もいもい!!』『もいもい~??』と読み方を変えるだけで
まだ言葉の理解ができない赤ちゃんでも食いつきが良く、ボロボロになるまで読んだ絵本です✨
1〜2歳ごろ(言葉が増え、意味を結びつける時期)
| タイトル | 特徴 | 知育ポイント |
|---|---|---|
| 『きんぎょが にげた』五味太郎(福音館書店) | きんぎょを探す遊び絵本 | 観察力・記憶力・視覚認知の発達に効果的。 |
| 『だるまさんが』かがくいひろし(ブロンズ新社) | リズムと動きが楽しい | 擬音語・動詞の習得、全身を使った模倣遊びにも。 |
| 『ごぶごぶ ごぼごぼ』駒形克己(福音館書店) | 音のリズムとカラフルな抽象絵本 | 色・形・音への反応を育て、感性の土台に。 |
| 『おつきさまこんばんは』林明子(福音館書店) | やさしい夜の絵本 | 生活の流れ(昼→夜)と情緒の安定をサポート。 |
『きんぎょがにげた』は、探す系(のちにウォーリーやミッケ!)につながる、イラストの中からきんぎょをさがす絵本です。
こちらも文章は「どこ?」や「こんどはどこ?」だけですが、親子で一緒に探す行為は、この年齢からできるんだ!と実感した絵本でした。
また『だるまさん』シリーズは、楽しい擬音語が盛り沢山!だるまさんのポーズを真似したり、同じ顔をしたりすると楽しい絵本です。
種類が沢山あり、ハマると3冊ともとっても楽しく、繰り返し読みたくなるようで何度も何度も読んだ本でした。
2. 語彙と会話が広がる、言葉のブーム期(2〜3歳)
ことばが出るようになると、何度も同じ本を読む中で、語彙が自然に増えていきますよね。本のセリフを真似したり、日常の言葉に混ざって出てくるようになる時期だと思います。
選ぶポイントとしては【セリフを真似しやすい、何度も何度も読める本】でしょうか。
2~3歳ごろ(トイレや着替え、挨拶など生活スキルを学ぶ時期)
| タイトル | 特徴 | 知育ポイント |
|---|---|---|
| 『しろくまちゃんのほっとけーき』 わかやまけん(こぐま社) |
ホットケーキを作る過程を丁寧に描写。擬音が楽しい。 | 生活習慣の理解ができる。擬音語で言葉が豊かに。 順序・手順の認識。 |
| 『ぴょーん』 まつおかたつひで(ポプラ社) |
動物たちがジャンプ!体を使って読める絵本。 | 動作と言葉の結びつきを意識できる。 真似ることで運動感覚・模倣力。 |
| 『とんとんだあれ』 わだことみ(岩崎書店) |
ドアをノックすると次々に登場人物が出てくる。 | あいさつ・順番・やりとりの理解に。 社会性の芽生え。 |
| 『どうぶついろいろかくれんぼ』 いしかわこうじ(ポプラ社) |
型抜きしかけ絵本。色や形、動物が学べる。 | 観察力・図形認識の発達に効果的。 動物の名前や色の習得。 |
| 『アンパンマンのとびだすえほん どうぶつ』 やなせたかし(フレーベル館) |
しかけ絵本。スライドを引いたり押したりしながら動物が学べる。お出かけにぴったりサイズ。 | スライドで仕掛けを動かす仕組みで指先の力加減や細かな手の動きを鍛える。 動物の食事や習慣の取得。 |
| 『ぶーぶー じどうしゃ』 山本忠敬(福音館書店) |
さまざまな自動車が登場する名作。乗り物好きに。 | 働く車の名前と役割の理解に。 分類する力が育つ。 |
| 『ノンタンおしっこ しーしー』 キヨノサチコ(偕成社) |
「しーしー」という擬音を繰り返し、トイレ行動を身近に感じさせる。 | 「しーしー」という言葉・音を理解し、トイレと結びつける。 トイトレのイメージに。 |
| 『ふみきりくん』 えのもとえつこ(福音館書店) |
ふみきりくんの一日。実際にある電車が出てくる絵本。電車好きには堪らない絵本。 | 「ふみきりくん」という擬人化された機械が主人公のため、想像力・視点の転換ができる。 |
しろくまちゃん、どうぶつかくれんぼ、アンパンマンのとびだすえほん、ノンタンなど、シリーズものが好きで、お決まりのパターンが楽しく何種類も読みたくなる時期でした。
また、『とんとんだあれ』や『アンパンマンのとびだすえほん』のような、小さくて持ち運びしやすいしかけ絵本も外出時に便利で持ち歩いていました。
この頃から、好きなもの(動物、虫、電車、車など)の図鑑を見るのも好きでした!
我が家が初めて買った図鑑は、『はじめての図鑑 身近な生き物』です。子供向けの図鑑はもちろん、大人向けの図鑑でも写真が沢山載っていれば楽しめます。
我が家は、2~3歳のころ路線バスが大好きだったこともあり、『路線バス大全』のような一般向けの本を買いました。子供向けではないので紙が薄かったり、先がとがっているので注意は必要ですが、ボロボロになるまで読んだ(正確に言うと見た)思い出があります✨
気軽にえほんを始めてみよう!
絵本の好みや、興味のあることは子どもによって千差万別ではありますが、最初に手に取る本に悩んでいる方や、新しい本を探している方の参考になれば幸いです。
どんな本がいいか分からない…図書館の本を汚すのが怖くて借りられない…という方には、中古の本を毎月3冊チョイスして送ってくれる、絵本のサブスクもおすすめです!
特に0~3歳児連れで本屋さんに行くことはハードルが高く、よだれで汚したり、嚙んだりしがちの時期には非常に便利です…✨
絵本のサブスクはこちらをチェック👇
次回は、3歳~5歳にお勧めの絵本をご紹介します。お楽しみに!